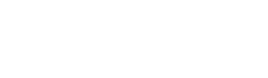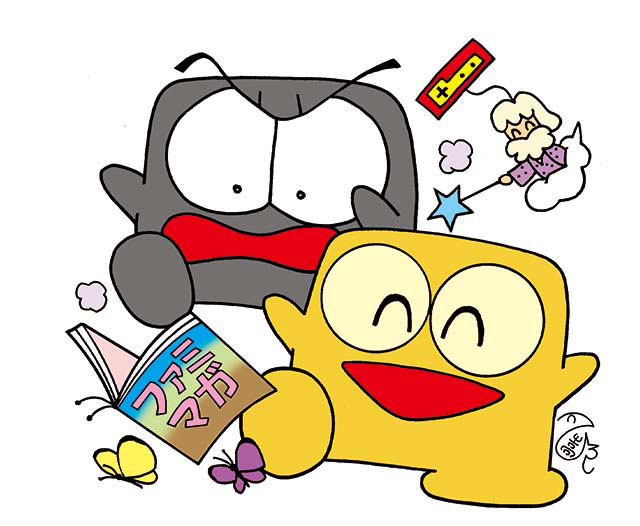目次 [非表示]
【第8回リレーブログ】元ファミマガ編集長、山本直人様
私こと、さあにん@山本直人が『ファミリーコンピュータMagazine』(以下、ファミマガ)を発行していた徳間書店に入ったのは、1984年の秋のことであります。PC情報誌『テクノポリス』のアルバイトとして入社し、そのまま『ファミマガ』のスタッフになるという流れでありました。
で、そもそもそれまで私が何をしてたのか。今回のテーマは「ゲーム雑誌編集者」でありますが、18歳で東京に出てきてから、実はずっと「編集」のお仕事をしていたのであります。そして遡れば、3歳の時から「メディア」という仕事を目指して年を重ねてきたのでありました。ゲーム雑誌の編集者としての私を語るとなると、私のほとんどを語ることになります。やや長くなるかと思いますが、お付き合いください。
貸本屋に通い詰めた幼児時代
現在54歳であります私が、最初に触れたメディアは「テレビ」と「マンガ」でありました。ただ、テレビは無料で見られますが、本は子供がしょっちゅう買うにはまだまだ高価すぎる時代。もっぱら利用していたのは「貸本屋」でありました。現在はTSUTAYAなどで復権している「貸本(レンタル)」ですが、昭和40年代は本屋より貸本屋が主流。マンガは貸本屋で借りるものでありました。折しも週刊マンガ雑誌が創刊され、ブームが始まる直前。今はもう無くなってしまった虫コミックスや、曙出版発行のコミックスを中心に、藤子不二雄先生、赤塚不二夫先生をはじめ、ありとあらゆるギャグマンガを読みふけっておりました。6歳になるころには貸本屋にあった本をほぼ読破し、2周目に入る形に。家に帰るとマンガとテレビに夢中になっていた幼児時代でありました。
幼児時代は岡山県で暮らしておりましたが、小学3年生の時に高知県に引っ越し。そこで家に置いてあった『週刊マーガレット』を読んで、私はファーストインパクトを迎えるのであります。放任かつ若干裕福目の過程に育ていました私は、その日から本屋に通いつめ、ありとあらゆる少年少女マンガ雑誌を買うようになりました。少女マンガの面白さに目覚め、雑誌を読みふける私が、雑誌の中で一番興味をもって見ていたのが「表紙」と「目次」と「背表紙」でありました。
御多分に漏れず、マンガが好きな子供であった私は「マンガ家になりたい!」と思い始めておりました。手塚治虫「マンガのかきかた」をはじめ、マンガ家入門書を何冊も読み、いちばん「やりたい!」と思ったのが「肉筆回覧誌」を作ることでありました。自分で白紙の計算用紙に描いた稚拙なマンガを束ね、表紙を付け、裏表紙と目次を付け、挙句の果てに「奥付」(発行日等を記載したもの)を入れるというふうにいわゆる「商業誌」のまねごとを始めたのであります。これが私の「編集者」ことはじめでありました。
クラスで肉筆回覧誌の発行がブームとなる
ところが、そのうちに意外なことが小学校のクラスで起こったのであります。マンガ雑誌の部数が伸び、新しい雑誌が創刊され、マンガ家の募集がコンテストとしてあちこちで始まります。それに伴いマンガを描くことが子供の間で流行ります。で、私のいた小学校のクラスでは、みんなの描いたものをまとめた肉筆回覧誌が何冊も発行される始末。面白いマンガを描く人を自分の本に取り込もうと、派閥争いのようなものまで起こる事態になり、学級会(ホームルーム)の議題にまで発展する騒ぎになったのでありました。
いろいろなトラブルが起こり、やがてクラス内で発行されていた肉筆観覧誌はすべて廃刊されてしまいます。そんな中、私だけが密かに発行を続けておりました。
同じ頃、テレビ、マンガに続いて私がハマり始めるのが「テレビゲーム」であります。ポンから始まり、「ハッスル」「アクロバット」「トランポリン」など、目についたものは全部1度は遊んでみました。前述の一件が収まった1976年、小学6年生の時に出会ったのが「ブロックくずし」こと「BRAKE OUT」。駄菓子屋に置いてあったアップライト筐体を、ともだちとみんなで独占して、何時間も遊んだのであります。
コンピュータが映像を描く。そしてそれがなんだか「面白い」遊びになってる。メディア好きの私は、そんな「画面」に釘付けになっていったのであります。
「だっくす」という雑誌
とはいえ、当時「コンピュータ」なんてものは、家庭で手元に置いておけるようなものではありません。あいかわらず「マンガ」がいちばんの楽しみであった私は、ある壁にぶつかってしまいます。それは「絵がうまくならない」ということであります。それでも読むこと、描くことが好きだったわけでありますが、自分が思ったように描けない。つまりは「面白い」ことを伝えられないというジレンマに陥ってしまいました。
そんな中学2年のある日。本屋で手にとった本が『だっくす』という本でありました。ジャンル表題は「まんが専門誌」。とはいえ、中身はいわゆる「評論誌」「情報誌」というもの。手に取り、中身を見た私に俗な言い方で言えば「背中に電流が走り」ました。これが私のセカンドインパクトであります。
「この方法があったか!」
それまでの私は「自分で」モノを作って「面白い」を人に伝える。ということだけを考えておりました。しかしこの「だっくす」は、だれかの創った「面白い」モノを見つけて、人に伝える。という本でありました。本の中には、いろんな作品の評論や紹介が、いろんな人のコトバでいっぱい詰まっておりました。そう、これが私が「情報誌」という本を、体感で捉えた瞬間なのであります。
そこから私の作る本は変わりました。自分の読んでいる好きなマンガの紹介を書き、ページを構成し、本にまとめる。本の中にはいろいろなコーナーを作り、あいかわらず目次や表紙、裏表紙なども作っておりました。私の編集者としての流れは、ここで大きく「情報誌」として舵を切ることになったわけであります。
※中学2年生の時、書店で見つけて購入した『だっくす』。これが全国発売第2号。下の方にお名前のある「ケン吉」さんは柴門ふみ先生のアマチュア時代のペンネーム。「ポポロクロイス物語」のコミック版など、けっこうその後のお仕事に関わる作品が、今思うと掲載されていた。
スペースインベーダーとマイコンがやってきた
中学3年の時、進学塾の夏期講習で向かった高知市内のゲームコーナーで、私はついに「スペースインベーダー」に出会います。今までと違う「キャラクター」を持ったゲーム。まだ、世に出たばかりの「レバー」のないバージョンでしたが、講習に通う間、延々と遊んでおりました。そこで友人と「全部倒したらどうなるんだろうね?」などと会話しながら、講習が終わってからも「あー、インベーダーが遊びたい」と考えておりました。残念ながら当時住んでいた町には、前述の駄菓子屋と小ぶりなショッピングモールくらいにしかゲーム機がなく、新しいゲームがすぐに導入されるというようなことはありませんでした。
高校生になり、高知市内の高校に通い始めた私は、マンガに続きTVゲームにも思いっきり時間を割き始めます。何より高知市内にはゲームセンターがありました! そして最近また注目されております「自販機コーナー」にもテーブル筐体が。あちらに「コスミックゲリラ」が導入されたと聞けば、自転車で1時間半かけて遊びに行き、駄菓子屋に「パックマン」が入ったと聞けば、閉店まで遊び尽くし、「クレイジークライマー」を玉の取れたレバーで遊び、「フリスキートム」でカンストし、「ジャンピューター」でマージャンのルールを覚える。そんな日々を送っておりました。手書きからガリ版に、プリントゴッコにと形態を変えていた私の「同人誌」には、いつの間にか「TVゲーム」の紹介と、攻略のコーナーが(読者であった女子からは不評でしたが)連載されておりました。
次にやってきたのが「マイコン」ブームであります。ゲーセンでしか遊ぶことのできなかった「TVゲーム」を、自分で作ることができる。カセットテープを読み込めば、簡単に別のゲームが遊べる。そしてアクションやシューティングでない、別の面白さのジャンルのゲームが遊べる。自宅にはコモドール社の「CBM3032」がやって来て、国産のマイコンとはまた違ったゲームを遊んでおりました。ゲームはどんどん私の生活を侵食しておりましたが、並行して、今度は任天堂のコピラスを使って湿式コピー印刷になっていた私の同人誌には、ゲストがコミックで参加したり、ついに背表紙を付けたりして、高知市内の書店5軒に5部程度を納品して販売してもらう本になっておりました。
※『murmur』最終号。この号だけコミケで販売した。特集は私に多大な影響を与えてくれた「はみだしっ子」の三原順先生。『murmur』では最終的に月2回刊行っていう無茶もやった。’97年にフリーになって作った「murmur’s GROUP」はこの本が原点。
東京での編集生活が始まる
1982年4月。いよいよ東京での編集をお仕事としての生活が始まります。とはいえ最初にはいったのは『だっくす』が名称変更し、その後いろいろあった後に新会社で復刊した『ぱふ』という雑誌の編集部。編集部といっても、スタッフは全員が20代。大学を卒業したばかりくらいの人の集まりです。イベント情報誌の『ぴあ』や『アニメージュ』に代表されるアニメ情報誌、『ログイン』などのマイコンゲーム情報誌など「情報誌」が一般認知され、部数を大きく伸ばしていた時代ではありましたが、『ぱふ』は部数も少なく全員がアルバイトスタッフに近い状態。1か月のお給料は4万5千円。ようするに私は親のすねをかじって、好きなことをしておりました。
「情報誌」を作って「面白い」マンガを「伝える」という目標を実行し、生活は至極充実しておりました。すでにオフセット印刷で、通販まで行うようになっていた同人誌の発行は、82年8月の「三原順特集号」で終結。『ぱふ』に集中しておりました。一方でTVゲーム生活も東京に出てきたおかげでさらに充実。24時間営業の歌舞伎町の「アナタのお名前ワ?」みたいな札で有名なロケテストの多いお店、洋ゲーの多かった一番街キャロットなどで時間が空けば遊びに行っておりました。一方で高知の実家は、かなり大きなチェーンとなっており、生活は仕送りで十分暮らせる形でした。おそらくはこのまま『ぱふ』での仕事を続け、時間が経てば高知に戻って自宅を継ぐことになる…。私にはそんな流れが待っておりました。
※『ぱふ』にいた時代に作ったとりみき先生の特集号。当時はコミックスを4,5000冊くらい所持していたのだが、ほとんどギャグマンガか少女マンガ。実は「北斗の拳」とか「キャッツ・アイ」とか、その後仕事で関わるのに全く読んでなかったりする。
ある日、突然に高知に戻ることになります。父親が倒れ、大きな事件の後、両親は離婚。当面東京に戻れなくなった私が入り浸ったのが「パソコンショップ」であります。パソコンの機種も増え、PC-6001のような廉価なものも登場し、BASICでもそれなりのゲームが作れるようになったその頃、私が作ったのがPC-6001の「WONDER HOUSE」でありました。同人誌を作ることをやめていた私は、その空いた時間を久々に「創作」活動に向けることになったのであります。その頃はソフトバンクなどPCゲームの流通に変化が起こっており、地方のパソコンショップから、さまざまなソフトが販売されるようになっておりました。それに乗っかる形で私は「WONDER HOUSE」の販売を、入り浸っていたPCショップに提案します。それがタスクフォーツ高知でのソフト販売であります。同時に、友人の作っていた「BUILDING HOPPER」も、私がプロデュースして販売をすることになります。パッケージなどを自分でデザインし、自分で印刷所に発注し、発売にこぎつけ、結果2本のソフトで合計8000本ほどを売り上げます。このお金は高知での生活の助けになり、我が家にはありとあらゆるパソコンが揃い、ついでにファミコンも本体と全ソフトが揃っているという状態でした。
※『ワンダーハウス』のパッケージ。縦長のものはVer.2で、正方形のものはVer.4。全部で4バージョンのパッケージがある。結構長く売れた作品。http://www.retropc.net/mz-memories/mz700/tfk.html にて、MZ版が公開されている。MZ版を除き、完全BASIC。
東京へリターンズ!
しかしながら、地方ショップのゲーム販売ブームは、それほど長く続かなかったのであります。家からの収入も、ソフト販売の収入も途絶え、仕事もない状態の私は、東京へ戻ることにします。残ったお金で『ぱふ』での仕事を続けながら、実家から最後に渡されたお金で部屋を借り、しかしながら「これでは暮らしていけない…」現実にぶち当たります。
「これは、もうひとつ仕事を探さなければ…(汗)」
とはいえ、ここまで「メディア」オンリー、その中でも「情報誌」のみを追いかけていた人生。となると選択肢は1つしか残っておりません。
「マンガと同じくらい好きな「ゲームの情報誌」に応募しよう!」
アルバイト情報誌を買い込み、掲載されていた『ログイン』にまず応募。結果、書類で落とされます。翌週見つけた『テクノポリス』に応募。面接に呼ばれ、即日で採用され、私の2つめの仕事が始まったのでありました。
最初の仕事はショーの取材。それから各ハード別の人気投票の記事を担当し、年末を迎え、明けて1985年の春。上司にこう伝えられます。
「ファミコンの本を作る予定があるんだけど、やってみたいと思う?」
パソコンでなく、テレビゲーム「情報誌」の仕事であります。一も二もなくOKし『テクノポリス』を離れるのでありますが、後に聞いた話だと「行かないでほしかった…」と。いやまぁ、並行してやっててもよかったんですがね。
ファミマガ人生始まる
※今もお仕事を続けている嵩瀬ひろしさんの「ディスくん」。いつもお世話になってます。
85年5月。『ファミマガ』創刊号の編集がスタートしました。私が何の作業をしたかなどは、少し前に書きました「超実録裏話ファミマガ」を読んでいただくとして、当時の私はまだまだ「マニア」と呼ばれる種族で、自分より薄い知識の質問には上から目線で答える、なかなかに嫌な奴でありました。「自分は知識が深い!」「私はこう思う!」「これは実はこうだ!」みたいな言動をひけらかす、まぁSNSなら陰で悪口を書かれるような奴でありました。
もともと『ファミマガ』編集部に、アーケードゲームの知識が深い人もいなかったため、私の性格は増長しておりました。いろいろとゲームの設定がいやらしいものや、隠しキャラなど「知っていて自慢する」「攻略方法を自慢する」みたいなものが当たり前だった時代ですから、そういうキャラの「マニア」が多かった時代でもあります。
そんな中「なんじゃ、このゲームは!?」と驚天動地の衝撃に襲われたの「スーパーマリオブラザーズ」であります。このあたりの経緯も前述の本にありますが、それまでのTVゲーム観がひっくり返る衝撃だったのであります。
『ファミマガ』の部数はどんどん伸び、「スーパーマリオ」の完全攻略本がベストセラーになる中、『ファミマガ』の創刊と同時に、忙しさが段違いになった私は『ぱふ』の特集原稿を落としてしまいます。ガンガンに怒られるのは当然。結果、私はその号で『ぱふ』を辞め、徳間書店の仕事一本での生活になったのであります。
そんな時、ひとつの仕事が舞い込みます。それが「ゼルダの伝説」の取説を作る仕事でした。はじめて京都の任天堂に行き、宮本さんと会い、打合せを行い、まだ未完成のソフトを手に取説の構成をし、原稿を描く。まだ任天堂に移籍する前の小田部さんからイラストのお話を伺い、編集を行っていくのであります。同時発売のロンチソフト「謎の村雨城」も別の担当が並行して取説を作っておりました。
まだまだ「マニア」さが抜けない私は、宮本さんにひとつの質問を投げます。
「スーパーマリオのハテナブロックには、なんで「?」が描いてあるんですか? (隠しキャラにしなかったんですか?)」
宮本さんの回答。
「だって「?」って描いてあれば、みんな叩くじゃないですか」
この言葉が私の「サードインパクト」であります。この日から私は、自己中心型の評価がんをやめ、第三者型の評価をするように、編集者としての方向がガラッと切り替わったのであります。『ファミマガ』が小学生向けの雑誌で、パソコン雑誌にあった編集者のノリを出さない情報誌だったのも功を奏しました。自分の好きなゲームだけでなく、他人の好きなゲームもその人の目で評価を受け止められる。編集者としての私の目が、そう切り替わっていったのであります。
私が企画した一連の本の中に『スーパーストリートファイターⅡ 完全攻略本』があります。しかし実は、私、『ストⅡ』が遊べません。というか『ストⅡ』に限らず格闘ゲームがまったく遊べません。コマンドが入力できないのであります。さらに「戦う」というのが苦手で、「ウォーシミュレーション」や「将棋・囲碁」、撃ち合うことも苦手なので「FPS」もまったく遊べません。しかしながら、毎日昼になるとゲーセンに消えていく編集部員、そのプレイを肩越しに見て、編集部でキャラクターの技談議に花咲かせるのをこっそり聞き、攻略本、連続付録、豪華版攻略本、コミカライズといった流れを編集者として仕事していったのでありました。
※『ゲーゼン天国』はゲーセンブームにのったスピンアウト増刊のように言われているが、実は『PS Mag』の前哨戦として、アーケードの資料を集めたり、広報とつながるために作った。
ですので実は、スーパーファミコン発売以降、『ファミマガ』を作った中での記憶は少なかったりします。メーカー特集の付録などをメーカーと共闘して作ったり、付録として付けることが大丈夫になったCDを付録にして『スーパーファミコンマガジン』を創刊したり、PSの発売準備として『ゲーセン天国』を刊行したり。節々の私がゼロから発案した企画は記憶していますが、毎号の細かな記憶はほぼ無かったり。
※『スーパーファミコンマガジン』の第1号。『超実録』にも書いたが、SFC CD-ROMの発売を見越して、将来は体験版を添付した本にしたかった。値段が高い割には予想以上に売れて、売り上げとしては『ファミマガ』を1号余計に発行したくらいあった。
※完全な趣味でやっていたゲームのコミカライズ連載の1冊「サムライスピリッツ」。内藤泰弘先生の初連載作品。大判にしてリバイバルするも、大人の事情で現在は絶版。
※「クラシックSFCミニ」発売に合わせて、『ファミ通』と行った交換広告。こういう子供っぽいブラックジョークやドキュメントを放り込むのが、実は私が大好きなことだったりする。なので「マンガトピックス」とか時折、細かくブラックなネタが入っていた。
情報誌は、ある意味消耗品(消えもの)ですから、編集者としては引きずられないように「記憶をゼロ」にするという癖が私についているせいもあるかと思います。そうしないと「第三者」の目になれないので、校了し、本が発売されると毎号気持ちはゼロリセットであります。
唯一『プレイステーションマガジン』は、創刊当時『ファミマガ』とは方針の違った本を作るために、自分を大きく出していきましたが、月2回刊になるころには「記憶をゼロ」にする流れに戻っていましたので、見返すと「あれ? この号はまだ私が編集長?」とか思い出せなかったりします。『ファミマガ』時代の細かな話や聞きたい話がある方は「超実録」を見ていただくか、上京した際に呑みにでも誘ってください。
ということで今はまた私は、高知のほうに戻っております。カルチャー系の情報誌は、だいぶ数も減ってしまっていますが、スキマ的にゲーム情報に関わった書籍などを作りつつ、高知でも紙やネットや場所を使って、何かを紹介する仕事に向かっております。次に私が「好きになる」モノは何なのか、また「記憶をゼロ」にしながら過ごす毎日なのであります。
さあにん@山本直人 プロフィール:2代目『ファミリーコンピュータMagazine』編集長。『ファミマガ』関係の増刊、ムック、攻略本などの編集を経て、『PlayStation Magazine』を創刊。フリーに転身後はゲーム雑誌・攻略本のほか、電子書籍などの仕事にかかわる。現在は出身地の高知県に戻り、南国市の地域おこし協力隊に従事しつつ、2020年開設予定の海洋堂との共同施設の開設作業等に関わりながら、自宅では相変わらずのDTP、編集作業を生業として作業中。最近のお仕事は『ゲームドット絵の匠』(ホーム社)、『ケツイ deathtiny 絆地獄たち』(エムツー)の初回特典冊子の編集など。ご連絡は、Twitter → @sarnin までどうぞ。